この日常を生きる
三島由紀夫の生涯をつらぬく通奏低音は日常への嫌悪である。
幼時の詩作「凶ごと」に始まり短編小説「日曜日」、エッセイ「終末感からの出発」などそれは多くの作品に顔を覗かせる。
三島にとって日常のantonymは劇であった。
「近代能楽集」では日常はおろか時間や空間さえも瞬時に飛び超えていく。
やがては劇にも飽きたらなくなり、「太陽と鉄」の告白を経て自己劇化の極致ともいうべき自決へといたる。
そんな三島が嫌い抜いた太宰治もまた日常を愛し切れなかった人だ。
処女小説集「晩年」から「葉」、「人間失格」まで日常との不協和音が響き続ける。
若く美しい女に手を引かれて心中するまで日常は太宰を解放しようとしなかった。
芸術でさえ彼らを日常から救うことはできなかったのだ。
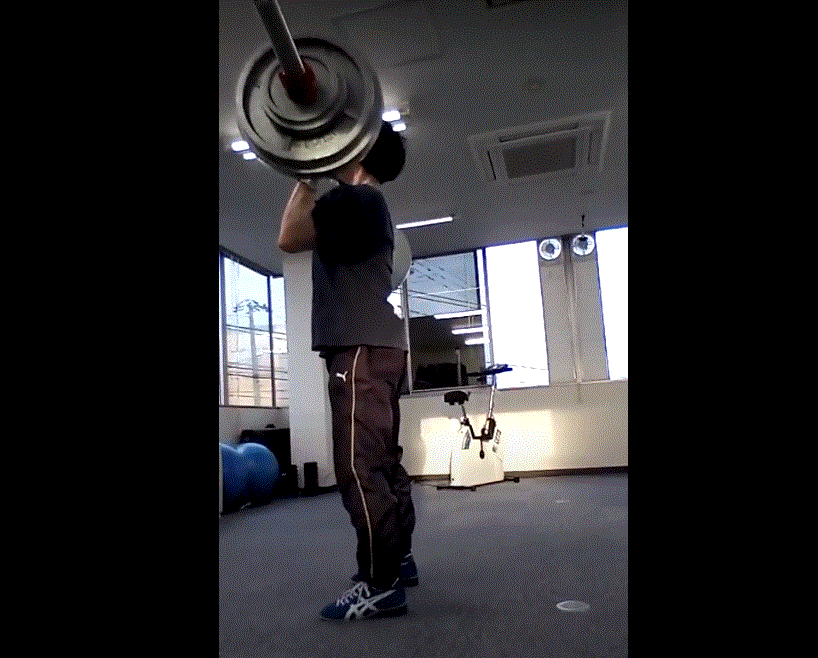
ことほどさように日常は退屈だ。
極度の退屈は苦痛をもたらす。
苦痛のもとで正気を保ち続けることは難しい。
ゆえに人は仕事や勉強、酒食や散財、そして運動や色事といった取るに足らぬ物事にすがって日常をやり過ごそうとする。
けれどもその程度で日常は私達を締め付ける手を緩めてはくれない。
さて、コロナ禍である。
コロナ禍は私達に日常という痛苦を改めて突きつける。
何もするな、何をしたって無駄だ。
考えすぎるな、考えたって無駄だ。
ただ生きろ、それ以外なにがある。
こうしたWeltschmerzに耐えきれぬ人々は当たり前に働き、行事に参加し、飲み食いに歩き、そして斃れていく。
さながら空爆のなか退屈に絶えきれず防空壕からさまよい出し、無残に殺される幼児のように。
この非常時、できるだけ普通に過ごそうとするのはWeltschmerzに耐えられぬほど弱い証左である。
ヨンデーは過剰なまでに感染防護に努めているパーソナルトレーニングジムだ。
それは気を抜いたが最後、疫禍に瞬時に焼き殺される日常を直視しているからに他ならない。
いま私達が立っているのはサルトルの「壁」の前である。
この日常を、正気を持って耐え抜けるかどうか。
私達の強さが試される。


